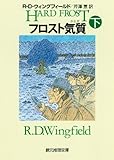「さようならフロスト警部。そしてありがとう」僕が小説の作者ではなくその主人公にこう語りかけたくなったことをR・D・ウィングフィールドさんが聞いたらはたして彼は草葉の陰でよろこんでくれるだろうか?
2009/7/8(Wed.)
R・D・ウィングフィールド『フロスト気質』(下)を読みおわる。下品なおっさんが苦労して難事件を解決する。ミステリーチャンネルのフロスト警部のことは名前だけは知っていたが、活字で読むのははじめて。それがこんなに面白いなんて、もっと長くてもこの倍くらいあっても、あと事件の二つや三つ余計にこんがらがってても大歓迎だった。「読まずに死ねるか!」と言ったのは内藤陳さんか。ひょんな気まぐれがなければこんな面白い本をうっかり僕は読まずに死んでゆくところだった。あぶねーあぶねー。下巻の後半あたりからそれぞれの事件が無事解決に向かう。まあこれはしょうがない。そのことで胸がすく思いがするのもまた事実である。ただしこれが悩みのタネなんだが、いつのまにかこっちは、事件の糸口が簡単に潰れたり、フロスト警部の直感がものの見事に外れたり、犯人(とおぼしき相手)にいいように翻弄されたり、署長に厭味を言われたり、同僚の警部に要領よく手柄をかっさらわれたり、と、そういう寄り道道草が楽しくて本を読んでいた。いっそこのまま事件が解決しないでくれたらいいのに、と願わずにいられない稀有な推理小説なのだった。最高。
のっけから自分の昔のweb日記の引用で申し訳ない。読めばわかるとおり『フロスト気質』の感想である。が『フロスト始末』を読んだ感想も基本まったく同じものだと思ってくれていい。僕がはじめてフロスト警部と出会ったのは僕がいまより8歳ばかり若いころのことだった。いまでもよく覚えているのだが図書館には誰かが返却した本を本来それが保管されるべく書架に戻す前に一時的に仮置きしておく台というか台車があって『フロスト気質』はそんな仮置き台車の上で偶然見つけて試しに借りてみた本だった。たまたま運よく上下巻揃っていたし思わず引くくらいの分厚さの文庫本だったけれど正直お金を出して買うわけでもないし面白くないようだったら途中で(読むのを)やめていつでも返却すればいいやと軽い気持ちで借りてきた。それが「いっそこのまま事件が解決しないでくれたらいいのに、と願わずにいられない」とは警察小説にして推理小説の感想としてどうなんだろうと思うがいまより8つも若い僕は本気でそう感じたに相違ない破格の面白さだったのだ。
2009/7/27(Mon.)
刑事ものといえば、きょう読みおわったのがR・D・ウィングフィールドの『クリスマスのフロスト』。これはもう最高だったなあ。手放しで面白かった。複雑に絡み合ったミステリーもさることながら、フロスト警部の人情味あふれた優しさについつい惹き込まれてしまう。惚れてしまうがなっ。人間が手を染める悪事のうち、どこまでが許せてどこからが許せないか、たとえ身辺雑事のあらゆることにルーズであっても、フロスト警部はそこのところの基準だけは明確に持っている人だと思う。目こぼし出来る犯罪にはさっと目をつぶる。そのかわりその範囲の外にある犯罪には徹底的にしつこく喰らいつく。そうゆうところがもう完全にツボ。というわけで続編『フロスト日和』を引き続き読む。『クリスマスのフロスト』が500頁強。『フロスト日和』が少し長くなって700頁強。さらに第3作『夜のフロスト』が800頁弱。『フロスト気質』は上下巻で900頁強にも及ぶ長編と、だんだん長くなるのがこのシリーズの特徴。なによりそれが一番うれしい。
これまた言わずもがなだが『クリスマスのフロスト』の感想である。『フロスト気質』に感激して文末の解説からこれがシリーズものの第4弾であることを知った僕は矢も楯もたまらずシリーズ第1弾『クリスマスのフロスト』を読むことにしたのだ。さらに上記引用にもあるとおり読後間髪を容れず第2弾『フロスト日和』へと移行している。いかに無我夢中になったかわかるというもの。
2009/8/1(Sat.)
R・D・ウィングフィールド『フロスト日和』読みおわる。安定感抜群の面白さだった。しかも、泣かせる。長い物語のほんのおわりの方で、カチャカチャとスライドパズルが完成するがごとく、複雑に絡み合った事件はあれよあれよというまに解決する。そのときの爽快感たるや。そこに至るまでには十分捜査の手を尽くし、何度も失敗も繰り返してきているからこそ、とってつけたような謎解きにならないところがいいのだ。事件の中には陰惨を極めるものもある。よって手放しにハッピーエンドばかりとは言いがたいが、それでもまあモヤモヤが残ることはない。フロスト警部は、自分が完璧な人間じゃないぶん、他人にも完璧を求めない。そういう主人公の人間味に、周りの大部分の登場人物たちは惹かれ、読者の僕も大いに惹かれる。 『クリスマスのフロスト』と『フロスト日和』をたてつづけに読んで少し虚脱状態。このシリーズ第4弾『フロスト気質』ははじめに読んだから、あとは手元に『夜のフロスト』と、まだ翻訳されていない作品がひとつ(作者は2007年に死んだ)、それを楽しみに生きてゆけそう。
ここで一旦シリーズの発売年次というか本国・英国での出版とわが国で創元推理文庫から芹澤恵さんの翻訳本が発売された時系列を簡単に整理しておきたい。
1984年『クリスマスのフロスト』(翻訳出版1994年)
1987年『フロスト日和』(1997年)
1992 年『夜のフロスト』(2001年)
1995 年『フロスト気質(上・下)』(2008年)
1999年『冬のフロスト(上・下)』(2013年)
2008年『フロスト始末(上・下)』(2017年)
『フロスト日和』を読んでいる最中にも既に僕の懐にはシリーズ第3弾の『夜のフロスト』が用意周到に温められていたんですね。それと「まだ翻訳されていない作品がひとつ」とこの時点(2009年)で書いているのが第5弾『冬のフロスト』のこと。実は作者R・D・ウィングフィールドさんは2007年に鬼籍に入っていた。つまり実際には第6弾でシリーズ最後の作品『フロスト始末』も亡くなる前年に完成されその翌年には上梓されていたことになる。
2009/8/17(Mon.)
R・D・ウィングフィールド『夜のフロスト』を読みおわる。これで翻訳されたこのシリーズは全部読んだ。いずれもモジュラー型ミステリー小説の傑作。特に今作は、フロスト警部の下品さも事件の複雑さもシリーズ随一かもしれない。証拠をねつ造して犯人を自白に追い込むなんて日常茶飯事。署長とも徹底的に対立する。『ダイハード』ばりの大捕り物のアクションシーンまであるサービスぶりだった。強引さはあいかわらずだがいつもとは若干異なり、少々の苦味や混乱を残す結末。僕はシリーズの中ではこの『夜のフロスト』が一番好きかもしれない。ケチな窃盗から連続殺害事件まで、なにしろ次から次ぎに事件が起こり、容疑者とおぼしき人物が浮かんではそのアリバイが証明され、証拠が取りざたされては消えてゆく。しっかり整理しながら読むほうも大変だが、捜査責任者である当のフロスト警部が、そんな事件のことすっかり忘れていたよ、とたびたび思い出してくれるものだから、いい按配に最後まで落伍せずについてゆけるのだった。フロスト警部とはどんな人かと言うと、煙草をのむときはいつも、その場にいるみんなに順番に自分のパックを回してやるような人である。
「フロスト警部とはどんな人かと言うと、煙草をのむときはいつも、その場にいるみんなに順番に自分のパックを回してやるような人である」。これほんとそのとおりだ。『夜のフロスト』がシリーズのなかでいちばん好きかもしれないと興奮抑えきれずに書き殴っているが上の引用で挙げた煙草の箱をその場にいるみんなに回してやるシーンが毎回出てきて僕はそのシーンがフロスト警部シリーズのなかで本当に大好きだった。ましていまやテレビドラマも映画も煙草をのむシーンそのものがカットされる場合がほとんど。だから余計物語の本質や謎解きとはまるで無関係なそんなシーンが愛おしく感じるのかもしれない。
2013/06/28
R・D・ウィングフィールド『冬のフロスト』思った以上に時間かかったが読み終わる。シリーズ第5弾ともなればふつう感じるマンネリズムどこ吹く風の抜群の面白さだった。まあマンネリズムということでいえば、あらすじは基本全部いっしょなんだけどね。だけどそれは一応警察小説でありミステリ小説である以上、何らかの事件が起きて主人公が事件を解決する、という意味においていっしょだという程度に過ぎないんだよ。とにっかく面白いから。今回もおなじみデントン警察署は万年人手不足と相変わらずの検挙率の低さで、幼児の失踪事件、娼婦連続殺人事件、怪盗枕カヴァー事件などの同時多発的難事件・珍事件を抱えて大忙し。それに加え、英国のお国柄ともいうべきか、署内には大型バス一台分のフーリガンまでが居座りドンチャン騒ぎ。そんな中、われらがフロスト警部はきょうもきょうとて車輛維持経費の領収書の数字をごまかすべくセコイ作業に余念がないと。こんな話です。起きている事件は結構陰惨だし、幼児や娼婦といったいわゆる社会的に弱い立場の人たちが被害者となり、死人も多数出る。フロスト警部の捜査のやり方は、お世辞にもスマートで紳士的とは言えない。つまり下品であくどい。なんだけど、全編に通底するユーモアがそういう目をそむけたくなる部分を上手い具合にオブラートで包んでくれている。そしてなによりフロスト警部の人間性に僕は惹かれる。これは好みの問題だから、ダメな人にはとことんダメかもしれないけどね。でも例えば、ちっとも進展しない事件の経緯や悲しい結果を、被害者の家族へ伝えに行くいちばんツラくイヤな役目から逃げないところとか。みんながもう諦めて下を向いてるときでも、「何かひとつ見落としている。それがどうもわからない」といつも自問自答しているところとか。僕は好きだなあ。捜査方法は行き当たりばったりの勘が主流なので、彼の部下たちは無駄な時間と手間ばかりを強いられることになる。9割9分9厘が空ぶりに終わる。でも残りの1厘で奇蹟の渋い逆転ライト前ヒットが出て試合には勝つ。勝つがその代償も半端なく大きい。奇蹟と書いたが、一見無駄な捜査の積み重ねなくして、悲しいかなフロスト警部の場合、次の勘が降りてこないのだ。勘を頼りに結局ひとつひとつしらみつぶしにやることでしか事件解決に結びつかない。古今東西の名探偵のように閃きがまとまって空から降ってくるなんてことがないのだ。そこがたまらない魅力。ま、そうはいっても案外バカに出来ない観察眼を持っていて、現場のいろいろなものを見たないふうで見ていたりするのは、杉下右京さん並みに鋭いんだよね。今作は、自分比でしかないがいつも以上に敵もしたたかで用意周到だった。どんな綻びと見える点をついても憎らしいくらい少しも動じない。わりと最後の最後まで事件解決に手間取り、さすがに僕も「どうせ最後には……」と悠長に構えていられる気分ではなくなった。つまりギリギリまでハラハラドキドキした。警部の「くそっ」と毒づく回数がいつもより多く、今度こそお手上げだよと弱音を吐く回数もいつもより多かったように思った。
「勘を頼りに結局ひとつひとつしらみつぶしにやることでしか事件解決に結びつかない」我ながら上手いことを書いているなあといま読み返してもそう思う。フロスト警部は類稀なる勘が閃くスーパー刑事でも古今東西名の知れた名探偵でもない。 僕はこの小説を読んでいつも思うのは勘というかちょっとしたフックがかかるかかからないかの違いがフロスト警部とその他の大勢の刑事たちとの差なんだろうなあと。事実フロスト警部の直感はたびたび的外れなことがある。それでも勘を頼りに捜査員一斉ガサ入れを強行してその結果無駄だったことがわかったとしてもそれでひとつの嫌疑が晴れることを由とするというふうなのだ。そういう地味な積み重ねの最中でもフロスト警部の事件への足掛かりというかフックが聞き取れるか聞き取れないかくらいの小さな音をたててカチッとかかる瞬間がある。それを漏らさず聞けたときの僕の高揚感たるやもうその瞬間のためにだけこの長い小説を読んでいるのだと言っても言い過ぎではないくらいだ。今回の『フロスト始末』のなかでも何度かそういうシーンに出くわす。例えばこんなところ。
だけど監房の戸口のところでルイスは足を止めて振り返った。「病原菌のせいなんです」とルイスは言った。「うちの息子が死んだのは病原菌のせいだった。だから、あたしがあんなことをしたのも、もとはと言えば病原菌のせいなんです」
そのとき不意に、しかるべき理由など何ひとつないはずなのに、フロストの胸の内で疑いが頭をもたげた。嫌な予感がした。とてつもなく嫌な予感だった。
奥さんを殺してバラバラに切り刻んで捨てたと自供する男(ルイス)に対してあいつが犯人だとかそうじゃないとかいう勘とも違うもっと漠然とした嫌な予感程度のことをフロスト警部は感じる。これがフロスト警部のフックだ。この嫌な予感は直截的に奥さん殺しの事件解決に結びつくことはなくでも結果まったく別の事件解決の糸口に収斂していくという具合にね。勘も見込みも張り込みもガサ入れも防犯カメラの解析もなにもかも失敗続きに終わってもそれらひとつひとつがまるで無駄で無意味だったってことにはならないのはこのときの微かなフックが後々効いてくるからなのだ。さてその『フロスト始末』だがまあ例によって今度のデントン署も署長のマレットが点数稼ぎのため麻薬の密輸摘発の合同捜査に署員の半分を貸し出してやったせいで尋常ならざる人手不足に陥っている。これも例によって領収書の6という数字を8に書き換えることに余念がないフロスト警部の元に次々と事件の報告が飛び込んでくる。例によって犬が人間の足をくわえてきたという事件。例によって何人もの少女が行方不明になっているという事件。例によってまだ年端もいかない少女が強姦されるという事件。例によってスーパーに毒物が仕掛けられるという脅迫事件。例によって小児性愛者のパソコン画像や写真が押収されるという事件。それがほとんどいちどきに雪崩を打って押し寄せてくる。ところが我らがフロスト警部はといえばあいかわらずの寝不足に空腹を抱え「片足を落としたってやつが遺失物届を出しにきたら、届いてると言ってやれ」と威勢のいいことを言って憚らない。下品なジョークを飛ばしいまならセクハラ・パワハラ・差別発言などですぐにも訴えられそう。なのに憎めない。部下からも絶大の信頼と親愛を得ている。一方事件そのものも日本の刑事ドラマでよくあるようなウェットな感じがちっともしないのだ。事件の背後に犯罪者のやむにやまれぬ情実があったなんてことはほとんど微塵も匂わせない。ドライというかなんというか狡猾なやつや残酷なやつや異常性愛者や小児性愛者は理屈ではなくこの社会に厳然と存在するのだというまずそこからスタートしている。小説なのに目を覆いたくなる耳を塞ぎたくなる事件ばかりが立て続けに起こる。ほんとハードボイルドだなあとしみじみ感じるのはそのせいかもしれない。そして『フロスト始末』では作者が自らの死を悟っていたからなのかどうか主人公であるフロスト警部が絶体絶命の危機を迎えるのがいちばんの読みどころなんですよね。文字どおり命の危険に晒される場面もあるがそれよりなにより慣れ親しんだデントン署を去らなければならない事態が出来するのだ。それもこれも今度のフロストの敵は事件の犯人というよりも同じ署内の新任の主任警部のジョン・スキナーだったという。スキナーとマレット署長が企てたフロスト警部追放作戦にまんまとひっかかりあわや解雇?! 転勤?! というギリギリのところで(注:ネタバラシすると)なんと首謀者のスキナー主任警部が殉職してしまう。
「きみはスキナー主任警部を毛嫌いしていた。気に食わない相手だから、死んでもかまわないと思っていたのだろう? スキナー君を殺したのは、フロスト警部、きみだ。きみが殺したようなものだ」
フロストは何も言わなかった。そう、確かにスキナーのことは毛嫌いしていた。ああいう根性のやつとは、とことんそりが合わないと思っていた。そういう相手が死んだのだ。だが、たとえそういう相手だとしても、死んだことについては気の毒に思う――いや、本心からそう思えるか?
とフロストは胸の内で自問した。本音を言えば、心のどこかでこうなることを望んでいたんじゃなかろうか?(本文引用)
「あんたのことは、いけ好かない野郎だと思ってたよ」死体に向かって、フロストは言った。「死んでほしいと思ってたわけじゃないけど……でも、正直言って、こんなことになって気の毒だとは、どうしても思えなくてね」(本文引用)
これによりスキナーが大切に保管していたフロストをデントン署追放に追い込んだ証拠の改ざん書類を保管していたキャビネットの鍵がフロストの手元に入り無事一件落着。前にも書いたけどフロスト警部は警察官として決してスーパーマンではない。特別優秀でないどころか証拠隠滅も捜査令状がないままの家宅捜索も場合によっては犯人をでっち上げることすらやりかねない。卑劣な犯罪を憎むあまり違法捜査もなんのそのというある意味困った警察官だ。と同時に人間としても上の本文引用からも察せられるようにおよそ完ぺきな人間ではない。けれどもそれによってフロスト警部の魅力がなんら損なわれることはないのだ。むしろこういう人間臭いフロスト警部だからこそ僕らの愛するフロスト警部なのだ。作者の死によって今後もう新しいフロスト警部シリーズを読む機会は永遠に失われてしまった。無念でならない。これまでの同シリーズを翻訳してくれた芹澤恵さんに感謝します。というわけでいちばんはじめの一文に戻ろう。
さようならフロスト警部。そしてありがとう。